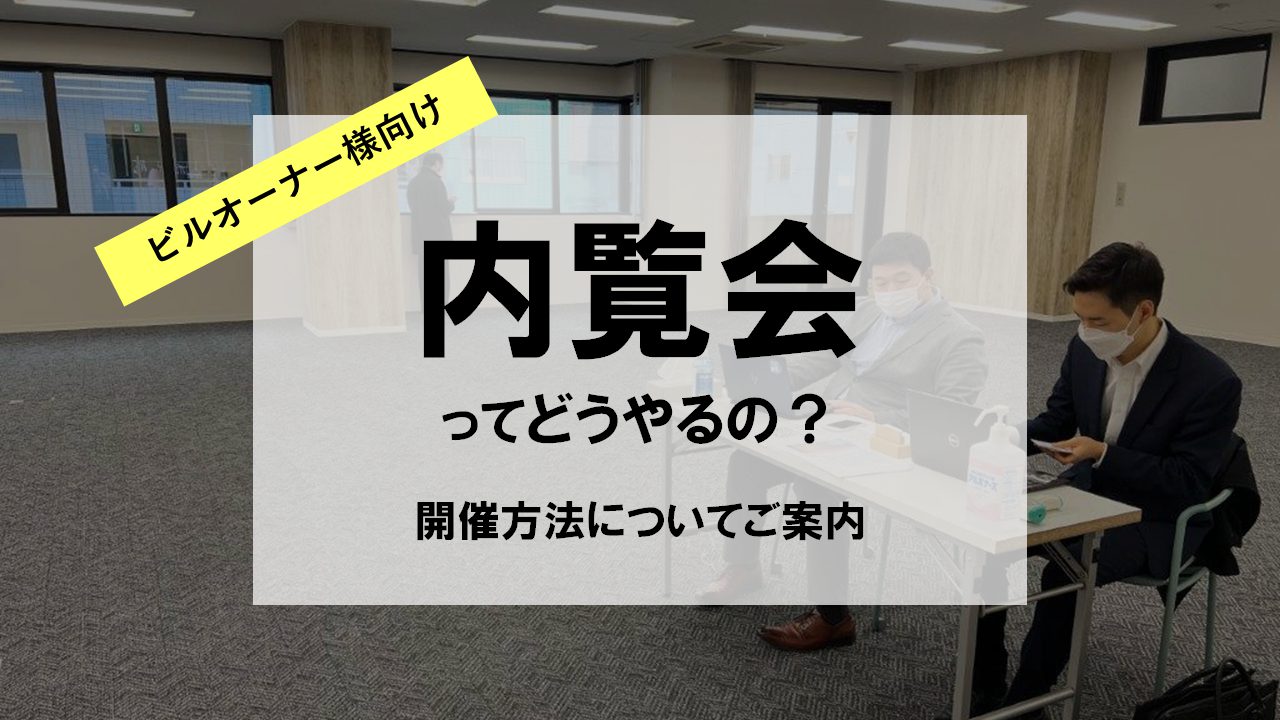オフィスビルやテナントビルを所有するオーナーにとって、空室対策は経営の根幹を揺るがすテーマです。
その有効な手段の一つが「内覧会」です。現地で物件を体験してもらうことで、資料や写真だけでは伝わらない光の入り方や共用部の雰囲気を来場者に理解してもらえます。しかし、実際に内覧会を開催する際に最も重要なのは「誰に向けて実施するのか」を明確にすることです。
内覧会のターゲットは大きく分けて二種類あります。ひとつは、最終的に契約をする可能性のある エンド顧客(テナント企業)、もうひとつは、テナントを紹介してくれる 仲介業者 です。
両者にアプローチする目的や伝えるべき内容は異なります。したがって、ターゲットごとに戦略を立てることが、成功する内覧会の条件となります。
仲介業者向け内覧会の位置づけ
仲介業者はリーシングの最前線に立ち、日々多数のテナント企業と接しています。そのため、まずは仲介業者を対象に内覧会を開催するのが一般的です。仲介業者に物件の魅力を理解してもらえば、自社の顧客に積極的に紹介してもらえる可能性が高まります。
当社ではメール配信を活用し、約500社・1,200名の仲介担当者に告知を行っています。開催曜日は火曜・木曜・金曜が多く、週末や月曜は避ける傾向にあります。来場者数は多ければ良いというわけではなく、同時期に複数の内覧会が重なると分散してしまうため、スケジュール調整も大切です。開催時間は10時から17時の範囲が一般的で、午前中に仲介会社を集中的に招き、午後に法人を迎えると効率的です。
仲介業者向けの内覧会では、募集条件や賃料水準、周辺の成約事例といった「数字」に基づいた情報が特に重要視されます。現場での体験に加え、投資回収シミュレーションや将来の稼働率の見込みといった資料を提示することで、営業トークに活かしてもらいやすくなります。
エンド顧客(テナント企業)向け内覧会の位置づけ
一方、エンド顧客向けの内覧会は「体験価値の提供」がポイントとなります。周辺企業への告知を行う際は、外部の企業データベースへのメール配信や近隣へのポスティング営業を組み合わせる方法が有効です。これには3〜5万円程度の費用がかかる場合がありますが、新規開拓につながる可能性があるため投資効果は高いといえます。さらに、既存顧客には営業担当者を通じて直接招待を行い、内覧を促進します。
テナント企業にとっては「このオフィスに入居すれば自社の社員がどう働けるか」が最大の関心事です。そのため、家具や仮設レイアウトを設置して入居後の働き方をイメージできるようにし、エントランスやラウンジでの過ごし方も含めて演出することが効果的です。説明では「数字」よりも「体験」を強調し、クリエイティブな働き方、ブランド価値の向上、採用への好影響といったストーリーを語ることが求められます。
事前準備と告知方法
内覧会の準備は、誰をターゲットにするのかを明確にすることから始まります。ターゲットには仲介業者とエンド顧客(テナント)の二つがあり、それぞれに最適なアプローチを考える必要があります。仲介業者にはメール配信を中心にした広範囲な告知が効果的で、当社では約500社・1,200名の担当者に一斉告知を行っています。曜日は火曜・木曜・金曜の開催が多く、10時から17時までの時間帯で実施するのが一般的です。
一方で、エンド顧客向けには、周辺企業へのポスティングや外部データベースを活用したメール配信といった手段もあります。費用は3〜5万円程度かかりますが、新しい潜在顧客を呼び込む有効な方法となります。既存顧客への告知は営業担当者からの直接紹介が効果的で、信頼性のある情報源からの案内は来場率を高めます。
内覧会の告知をどう行うか
内覧会告知は単なる「お知らせ」にとどめず、マーケティング活動の一環として設計することが重要です。仲介業者向けの告知は、できるだけ広範囲にリーチさせ、情報を共有してもらうことを目的とします。告知メールには、物件の写真や特徴だけでなく、競合物件との差別化ポイントや内覧会で体験できる演出を盛り込むと反応が高まります。
一方でエンド顧客に対しては、よりターゲットを絞ったアプローチが必要です。周辺エリアの企業に配布するポスティングや、特定業種を対象にしたターゲティング広告などを組み合わせると、関心度の高い層を効率的に集められます。つまり告知そのものも「誰に何を伝えるか」を明確にすることで、来場者の質が変わり、最終的な成約率にも直結するのです。
会場準備と運営
会場では受付用のデスクとイスを設置し、名刺受けや飲み物、配布資料を整えます。必要に応じて外部レンタル(2万円前後)を活用するのも選択肢です。人員体制としては受付と案内を担当する2名程度が最低限必要で、規模が大きい場合はさらに増員すると安心です。
来場者にはただ物件を案内するだけでなく、物件の強みを「ストーリー」として伝えましょう。仲介業者には「相場よりどの程度高い条件で成約できるのか」を、テナント企業には「この空間が自社にどんなメリットをもたらすか」を、それぞれの関心に沿って説明することがポイントです。
アンケートとレポート作成
内覧会を通じて得られる最大の資産は「来場者の声」です。Googleフォームなどを活用し、アクセスや立地、設備、エントランスの印象、賃料条件、フリーレントの妥当性といった評価を収集します。仲介業者には「市場感覚」、テナント企業には「利用イメージ」を中心に回答してもらうと有益です。
回収したアンケートはレポートにまとめ、オーナー自身の戦略に反映するだけでなく、仲介会社へフィードバックすることで、次の紹介活動につなげられます。改善点を抽出し次回に活かすことで、内覧会が継続的な物件改善のサイクルを生むきっかけとなります。
内覧会情報をリーシングにどう反映させるか
内覧会で得られる最大の成果は、単なる「来場者数」ではなく「現場の声」です。アンケート結果や直接のフィードバックを丁寧に分析することで、次の募集戦略に活かせます。例えば「賃料が相場より高い」との声が多ければ価格設定を再考すべきですし、「会議室が不足している」との意見があれば、募集前に区画を調整することで競争力を高められます。
さらに、仲介業者の担当者から得られる情報は特に有益です。市場の最新動向や、他の物件での成約事例、テナント企業のトレンドなど、机上の調査だけでは得られない情報を吸い上げることができます。これらを整理し、レポートとして蓄積すれば、長期的なリーシング戦略の質を大きく向上させられるでしょう。
誰が内覧会を企画するのか
内覧会の企画運営は、オーナー単独で行うよりも、LM(リーシングマネジメント)会社が主体となって進めるのが一般的です。LMは物件の特性やターゲットを分析し、マーケット調査と連動させて最適な告知方法や演出を設計します。オーナーに代わって計画を立て、仲介業者や顧客に響くプレゼンテーションを実施することで、効果的な誘致活動を実現します。
オーナーとしては、LMに全てを任せるのではなく、自社の意向や将来的な物件運営方針を共有し、パートナーとして二人三脚で進めるのが理想です。LMの専門性とオーナーの意図を融合させることで、より効果的で収益性の高い内覧会が実現します。
まとめ
内覧会は、ターゲット設定から告知、会場準備、当日の運営、アンケート収集、情報の反映、そしてLMとの連携までを一貫した流れとして設計することが成果につながります。
仲介業者向けには条件や相場感を、エンド顧客には未来の働き方を、それぞれ適切に伝えることが求められます。さらに、開催後の情報をリーシング戦略に落とし込み、LMを中心とした体制で実行していくことが、オーナーにとって「内覧会を収益に変える」最短ルートとなるのです。