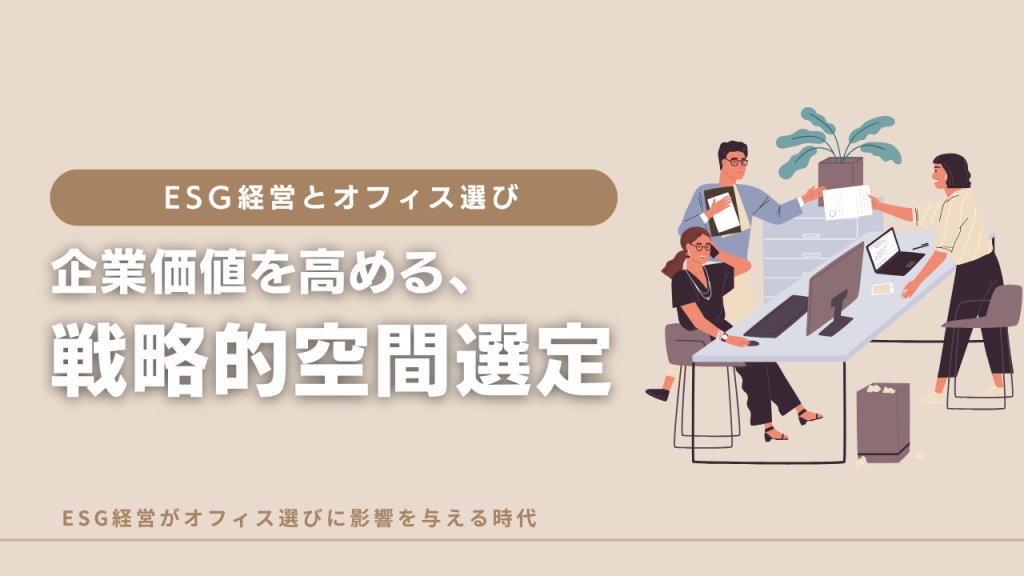仲介目線で語る「ウェルビーイングとオフィス選び」|オフィス不動産仲介業者が見る“働く人の幸福”と企業価値向上の関係

ここ数年、企業経営におけるキーワードとして「ウェルビーイング」が注目を集めています。これは単に「健康であること」に留まらず、働く人の心身の健康、生活の充実感、社会的なつながり、自己成長の機会など、幅広い幸福の概念を含んでいます。
私たちオフィス不動産仲介業者も、以前は「立地・賃料・面積」という3大要素を軸にオフィスを提案していました。しかし今、企業から求められるのはそれだけではありません。「従業員がより良い状態で働ける空間」を提供することが、採用や生産性、ひいては企業価値の向上に直結するからです。
ウェルビーイングの考え方が広がった背景には、政府や自治体による「健康経営」の推進があります。経済産業省が実施する「健康経営度調査」では、回答企業数が年々増加しています。例えば第7回(2020年度)では2,523法人が回答し、2014年度の493法人から大幅な増加が見られます (参照:Medifellow+7健康経営会議+7株式会社Avenir+7)。さらに第10回に当たる2024年度には、3,869法人が回答し、前年比で約10%増、2016年度以降の平均成長率は約23%にも達しています (参照:経済産業省)。
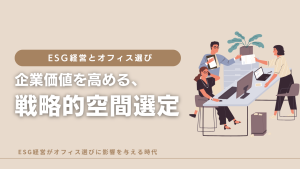
ウェルビーイングとは ― 幸福の総合的な状態をデザインする概念
国際的定義と背景
ウェルビーイング(Well-being)という言葉は、直訳すれば「良い状態」「幸福」を意味します。世界保健機関(WHO)は健康を「病気でないことや虚弱でないことだけでなく、肉体的・精神的・社会的に完全に良好な状態」と定義していますが、ウェルビーイングはこの概念をさらに拡張し、「人生全体における満足感」や「持続可能な幸福」を含む広義の概念として国際的に用いられています。
経済学や政策の分野では、GDPだけでは計れない豊かさの指標として「国民総幸福量(GNH)」や「OECD Better Life Index」などが登場し、ウェルビーイングは「物質的な豊かさ」から「心身・社会・環境が調和した豊かさ」へと評価軸を移す潮流の象徴ともなっています。
日本における行政的アプローチ
日本でも、内閣府や経済産業省がウェルビーイングの推進を掲げています。内閣府は「国民の幸福度や生活満足度を向上させることは、経済成長や社会の持続可能性と表裏一体」とし、指標整備や自治体のモデル事業を展開しています。経済産業省の「健康経営」施策もその一部で、従業員の健康や幸福を経営戦略として捉える流れが加速しています。
近年は「ウェルビーイング経営」という言葉も定着しつつあり、単なる福利厚生や健康管理を超え、組織文化や働く環境の在り方まで含めた包括的なマネジメントが求められています。

- オフィス移転のことが全然わからないけど大丈夫?
- はじめてで何から始めたら良いかわからない…
- オフィス移転はどんな流れで進むの?
- どんなオフィスが必要なのかわからない!
はじめて移転をされる方も、オフィス移転の面倒さを知っている方も、ニーズに合わせたご提案をいたします。
5つの主要領域(学術・実務で用いられるフレーム)
ウェルビーイングは多角的に捉えられますが、代表的な分類に「PERMAモデル」(ポジティブ心理学者マーティン・セリグマン提唱)があります。
- P(Positive Emotion):ポジティブな感情を持てること
- E(Engagement):没頭できる活動があること
- R(Relationships):良好な人間関係
- M(Meaning):意味や目的を感じられること
- A(Accomplishment):達成感を得られること
オフィスという視点で言えば、これらは空間設計・働き方・人間関係の文化づくりで大きく左右されます。たとえば、自然光が差し込むラウンジ(Positive Emotion)、集中できる防音ブース(Engagement)、コラボレーションエリア(Relationships)などは、物理的環境によるウェルビーイング支援の具体例です。
仮説:ウェルビーイングは「空間」と「文化」の掛け算
オフィス不動産仲介業者としての立場から見て、ウェルビーイングは「空間の質」と「組織文化」の掛け算によって最大化されると考えられます。
- 空間の質:温度・光・音・空気・色彩・家具配置など物理的要素が人間の心理・生理に与える影響は大きい。
- 組織文化:心理的安全性、多様性の尊重、成長機会、評価制度、コミュニケーションの在り方など。
どちらか一方が欠けても、真のウェルビーイングは実現しにくいのです。たとえば、最新設備の整ったオフィスでも、社内の人間関係がギスギスしていれば幸福感は高まりません。逆に文化は良くても、劣悪な空気質や窮屈な空間では健康面でマイナスが積み重なります。
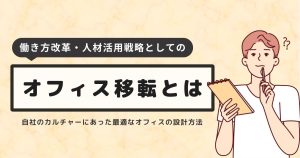
健康経営とウェルビーイング経営の違い
健康経営は、従業員の健康保持・増進を経営的視点から考え、組織の活力向上や業績改善を目指す取り組みです。具体的には、定期健康診断の充実、生活習慣改善のサポート、ストレスチェックなどが代表的施策です。
一方、ウェルビーイング経営は、その概念をさらに広げたものです。心身の健康だけでなく、働く人が「満足感」や「自己実現感」を得られる状態を目指します。職場環境、働き方、評価制度、人間関係、地域や社会とのつながりといった要素も含まれます。
つまり、健康経営が“体の健康”を守るための土台づくりであるのに対し、ウェルビーイング経営は“心と体と社会的充足”の三位一体を整えるアプローチと言えます。そしてその実現において、オフィスという「場」が大きな役割を果たします。

- オフィス移転のことが全然わからないけど大丈夫?
- はじめてで何から始めたら良いかわからない…
- オフィス移転はどんな流れで進むの?
- どんなオフィスが必要なのかわからない!
はじめて移転をされる方も、オフィス移転の面倒さを知っている方も、ニーズに合わせたご提案をいたします。
ウェルビーイングとオフィス環境の密接な関係
オフィスは、従業員が1日の多くを過ごす空間です。そこにおける快適性や心理的安全性は、仕事のパフォーマンスと密接に関わります。
1. 環境要素
- 自然光の確保:日中の自然光は体内リズムを整え、集中力や睡眠の質向上に寄与します。
- 換気・空気質:新鮮な空気は認知機能を維持し、感染症リスクも低減します。
- 音環境:適切な遮音や吸音は集中を助け、ストレス軽減に効果的です。
2. 心理的要素
- オープンで交流しやすい空間:偶発的な会話やコラボレーションが生まれる。
- プライバシー確保:集中作業やオンライン会議に適した個室やブースの配置。
3. 社会的要素
- 共用スペースの活用:ラウンジやカフェスペースが社内外交流を促進。
- 地域連携:周辺施設やイベントとの関係性が、従業員の生活満足度を高める。

行政データが示す健康経営の効果
経済産業省や厚生労働省の調査では、健康経営を推進する企業は離職率低下や採用力強化、生産性向上などの効果が見られることが報告されています。海外の事例では、Johnson & Johnson グループが世界250社・約11万人を対象に実施した健康教育プログラムにより、投資1ドルに対して3ドルのリターンが得られたとされています (参照:NECソリューションイノベータース+7Medifellow+7経済産業省+7)。
また、国内では複数のメタ分析に基づく研究により、健康増進を目的とした従業員向けプログラムによって、投資1ドルあたり1.40~4.60ドルのリターンがあったと報告されています(参照: RIETI)。
さらに、健康経営優良法人認定を受けた企業は、株価や業績面で市場平均を上回る傾向があるという分析も存在します。これは、健康経営やウェルビーイング経営が単なる福利厚生ではなく、投資家からも評価される戦略であることを示しています。

仲介業者ができるウェルビーイング視点の提案
私たちオフィス不動産仲介業者の役割は、単に条件に合う物件を紹介するだけではありません。ウェルビーイングを意識したオフィス提案では、以下のような付加価値を提供できます。
- 現状分析支援:従業員アンケートやヒアリングを通じたニーズ把握。
- 設計・レイアウト提案:ABW(Activity Based Working)やフリーアドレスなど、多様な働き方に対応。
- 環境性能の評価:ZEBやCASBEEなど、環境性能認証を持つビルの提案。
- 地域資源の活用提案:周辺の公園、カフェ、フィットネス施設など生活環境も含めた選定。
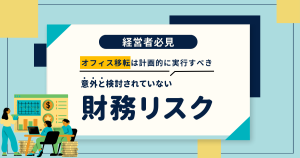
まとめ
ウェルビーイング経営は、企業の採用力・定着率・生産性を高め、投資家や顧客からの評価にもつながる戦略です。そしてその実践において、オフィスは最も直接的な影響を与える経営資産の一つです。
オフィス不動産仲介業者として、私たちは「立地・コスト・規模」という従来の物差しに加え、「働く人の幸福度を高める要素」を組み込んだ提案を行うことで、企業の成長を支えるパートナーになれると考えます。

- オフィス移転のことが全然わからないけど大丈夫?
- はじめてで何から始めたら良いかわからない…
- オフィス移転はどんな流れで進むの?
- どんなオフィスが必要なのかわからない!
はじめて移転をされる方も、オフィス移転の面倒さを知っている方も、ニーズに合わせたご提案をいたします。