オフィス更新時の賃料改定は拒否できる?賃料交渉の流れも紹介

最近、オフィスの更新時に家賃の値上げに関する相談が増えています。特に以下のような疑問が多く寄せられています。
- 「周辺相場と比べてうちの契約賃料は安いのでしょうか?」
- 「値上げの要請に対して拒否することはできるのでしょうか?」
現在の市況では、空室率が低く、オフィス賃料が上昇している地域も多いため、貸主からの「値上げのお願い」が増加傾向にあります。これに対して借主としては、どのように対応すべきかについて心配や疑問が生じることも理解できます。
正しい家賃交渉を行うためには、賃料がどのように決まるのか、値上げ通知に対処する方法、そして自身の権利と義務についての知識が不可欠です。賃料の変更を迫られた場合、借主としてどのようなステップを踏むべきかについて、以下で詳しく解説します。
そもそもなぜ家賃が上がるのか?
「え!?家賃って上がることあるの!?」と驚いている方も多いでしょう。
実は、オフィスの家賃は値上げすることがあります。たとえば、物価が上がってしまった場合や、固定資産税などの所有者・貸主側が払う税金が増えた場合です。また、周辺の土地の家賃相場とも比べて、明らかに安い場合にも家賃の値上げが生じることもあります。
これらは「借地借家法」という法律で決められており、このような「正当な理由」がなければ家賃の値上げをすることはできません。借地借家法は貸主からの一方的な値上げによって、借主が弱い立場にならないようにするための法律と言っても良いでしょう。

借地借家法とは?
借地借家法について具体的に解説しておきましょう。基本的に借主は弱い立場であるがゆえ、「借地借家法」によって借主を法律で守っています。主に借地借家法は、以下の4つの内容について決められています。
- 借地権
- 定期借地権
- 建物の賃貸借契約
- 定期建物賃貸借
簡単に言うと、その土地もしくは建物が賃貸借契約を交わす場合の、契約期間や存続期間、そして効力に関して決められた法律のことです。賃貸借契約を結ぶと、ほとんどの場合大なり小なりトラブルがつきものですので、このようなルールがなければ問題を解決することはできませんよね。
今回のテーマで取り上げている「家賃の値上げ」もよくあるトラブルの一つです。万が一、いい加減な理由をつけて家賃を上げようとしてくる貸主がいたとしても、入居者がその通告を拒否しても問題ないような仕組みになっています。借地借家法は、借主が不当な値上げに対して自身の権利を守るための重要な法律と言えるでしょう。

オフィス賃料改定の考え方
一般的に、賃料というのは固定化されたものという認識が多いようです。しかし、実は貸主からも借主からも、増額および減額の請求ができるというのはご存知でしたでしょうか。
借賃増減請求権という、いわゆる「賃料改定」が借地借家法第32条により定められているのです。
たとえば、坪単価20,000円で借りている物件を、契約更新時に坪単価25,000円にしたいと貸主側から相談されてしまうこともあるのです。
「いつでも貸主から賃料増額請求ができる」というのは好都合のようにも思えますが、もちろん理由なく賃料を上げることができるわけではありません。また、借主としては突然の値上げ交渉にどう対応すべきか準備をしておく必要があるともいえるでしょう。

貸主がオフィス賃料を増額できる理由
貸主が賃料の増額請求を行う際には、正当な根拠が必要です。不当な増額請求を防ぐために、以下のポイントに注意することが重要です:
- 周辺の賃料相場との比較: 賃貸市場において、明らかに不相当な高い賃料を請求することはできません。借地借家法に基づき、周辺の賃料相場と比較して過度に高い場合、増額請求が認められる可能性があります。賃料相場を調査し、自身のオフィスの賃料が適正であることを確認しましょう。
- 契約の特約条項: 契約書には特約条項が含まれていることがあります。特約条項には増額請求が禁止されている場合があります。契約書を注意深く確認し、特約条項が存在するかどうかを確認しましょう。特約がある場合、増額請求ができないことになります。
- 固定資産税や経済状況の変化: 貸主は、固定資産税の増加や経済状況の変化など、正当な理由に基づいて賃料の増額を要求することがあります。しかし、これらの変化が請求に値するものであるかどうかは検討が必要です。変化に対する詳細な説明や根拠が提示されるべきです。
正当な根拠がない場合、貸主の増額請求は無効とみなされる可能性が高いです。借主は自身の権利を守り、不当な増額請求に対して拒否する権利を行使することができます。増額請求に疑義がある場合は、法的アドバイスを受けることも検討しましょう。

オフィス賃料改定は拒否・拒絶できる?
オフィス賃料改定において、拒否権の有無は新規賃料と継続賃料の契約形態によって異なります。
新しく不動産を契約する際の賃料で、市場において成立する適正価格を示します。新規賃料は通常の市場賃料とされ、借主が契約を拒否する権利があります。
賃貸借契約の継続の際に当事者間で合意される賃料です。相場に基づく価格に加え、従前の賃料をベースにして話し合われ、お互いの経済的価値を反映した金額となります。通常、借主は提示された継続賃料を拒否する権利があります。
ただし、定期借家契約は再契約のたびに新規賃料で契約を行う形態です。したがって、定期借家契約の場合、再契約の都度新規賃料が適用され、借主はそれに従う必要があります。
ただし、一部の定期借家契約では再契約時に値上げが行われないこともあります。契約内容は個別に異なるため、契約書を注意深く確認し、新規賃料と継続賃料の違いを理解することが重要です。
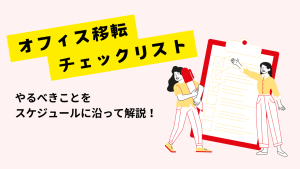
賃料交渉の流れ
継続賃料は通常、改定されないものと考えられています。最初に賃貸人と賃借人の間で契約が成立する際、お互いの信頼関係が築かれ、その契約に基づく賃料が尊重されるべきだと一般的に認識されています。しかし、時には賃貸契約の改定が不可避とされる場合もあり、この際にはできる限り両者にとって影響が少ないように配慮されるべきです。この点は借地借家法第32条に基づく賃料改定・変更の必要性でも強調されています。
継続賃料は経済的要因だけでなく、法的または個別の事情にも影響を受けるものです。つまり、市況が適正であると思われても、契約当事者が同意しなければ賃料は変更されません。賃貸人と賃借人の間で継続賃料に関する合意が難しい場合、まずは裁判所外の交渉が試みられますが、解決しない場合は裁判所による調停、訴訟によって決着がつくこともあります。裁判所外の交渉から調停や訴訟に至るケースも珍しくありません。
継続賃料に関するトラブルが予想される場合、できるだけ早く弁護士事務所などに相談し、専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。また、周辺の相場を知るために不動産仲介業者に相談することも有効です。借主の立場からは、相場に合わない継続賃料を拒否する権利があります。しかし、交渉に当たる際には、賃貸オフィス専門の不動産仲介業者や法的専門家に依頼することが効果的かもしれません。借主と賃貸人の権利と法的要件を理解し、納得のいく継続賃料を交渉しましょう。日本の賃貸市場は賃貸人の権利が保護されている一方で、借主にも法的に認められた権利が存在します。適正な賃料を確立するため、相場や法的要件を考慮して継続賃料を取り決めましょう。
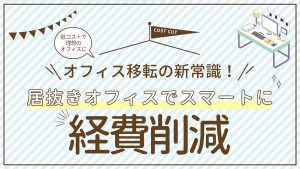
オフィス賃料値上げに対する具体的な準備
では具体的な準備はどのようにすればよいか解説していきたいと思います。
現在のオフィスマーケット資料を集める
オフィスの現状を知ることは、適切な判断を下すために不可欠です。具体的には、オフィスの面積を正確に測定しましょう。賃貸物件の場合、面積は家賃や契約条件に大きな影響を与えます。周辺の賃貸相場や建物の価値も確認し、自社のオフィススペースが適正に評価されているかをチェックしましょう。
また、オフィスの賃料は経済状況や契約更新時に変動することがあります。更新時期がいつかを把握し、家賃の変更通知がある場合に備えることも重要です。正確な情報収集と事前の準備が、オフィスの現状を把握し、最適な判断を下す手助けとなります。
周辺状況を確認する
オフィスの家賃を決める際には、単にそのオフィスだけを考えるだけではなく、周辺の土地や賃貸物件の相場も考慮する必要があります。周辺エリアの家賃相場を調査することで、自社のオフィスが市場価値と比較して適正な価格であるかどうかを判断できます。現代では不動産情報サイトを活用して、簡単に周辺の相場情報を収集することが可能です。また、不動産会社に相談して、同じような面積や間取り、設備を備えた場所の家賃を調査してもらうことも有効です。
これらの情報を総合的に考慮し、もし現在の家賃が適正であると判断される場合、家賃の値上げ通知があっても、自信を持って交渉し、拒否することができます。家賃交渉において、周辺の市場動向を把握することは非常に重要です。
オフィス仲介のプロに相談する
周辺のマーケット情報を収集する際には、賃貸オフィスに特化した仲介会社に相談することが多いです。彼らは市場トレンドや将来のマーケット予測、過去の賃貸市場の変動について詳細な情報を提供してくれます。プロの助言を受けつつ、賃料交渉に備えましょう。
コンサル会社に相談する
もし貸主からの賃料値上げ通知が非常に高額で、難しい状況になる場合、コンサルティング会社に相談することを検討してみてください。専門家のアドバイスを受けつつ、交渉戦略を立てることができます。特に大手企業や法的な複雑さがある場合、コンサルティング会社は有用なパートナーとなるでしょう。
これらのステップを踏むことで、オフィス賃料の値上げに対してより準備が整い、交渉時に強い立場を築くことができます。自身の権利を守りつつ、合理的な条件での合意を目指しましょう。

オフィス更新時の家賃交渉のポイント
家賃交渉を行う際には、貸主と入居者の両方にとって、値上げまたは値下げを要求する正当な理由が存在することが重要です。前述したように、周辺エリアの相場や同様の間取りの平均的な家賃などの情報を収集し、徹底的な調査を行うことが必要です。これにより、交渉の際に具体的なデータを持って相手に説得力を持たせることができます。
また、経済状況が悪化した場合や貸主が支払う固定資産税が増加した場合など、家賃の変更を検討する際には、これらの要因を相手にしっかりと伝えることが大切です。正当な理由があることを説明し、相手に納得してもらうための説得力あるアプローチが求められます。
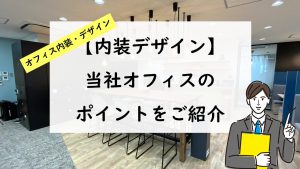
まとめ
オフィスの更新時に賃料改定を受ける場合、借主には拒否権がありますが、契約形態によって適用されるルールが異なります。新規賃料と継続賃料の違いを理解し、適切な対応を行うことが大切です。
新規賃料は市場における適正価格であり、借主は通常、提示された新規賃料を拒否する権利を持っています。一方、継続賃料は契約の継続時に合意される金額で、相場に基づく価格に従前の賃料をベースにして決まります。借主は通常、提示された継続賃料を拒否する権利を持っています。
定期借家契約の場合、再契約のたびに新規賃料が適用され、借主はそれに従う必要があります。ただし、一部の契約では再契約時の値上げが行われないこともあります。契約書を詳細に確認し、自身の権利と義務を理解しましょう。
賃料改定が争点となる場合、専門家や不動産仲介業者の助言を受けることが賢明です。正当な理由が示されている場合でも、適正な条件で合意を目指し、事前に準備を行い、周辺の市場情報を確認することが成功につながります。最終的には、法的手続きが必要な場合には弁護士に相談することを検討しましょう。家賃交渉は慎重に行うべきプロセスであり、正当な権利を守るために必要なステップを踏むことが肝要です。
